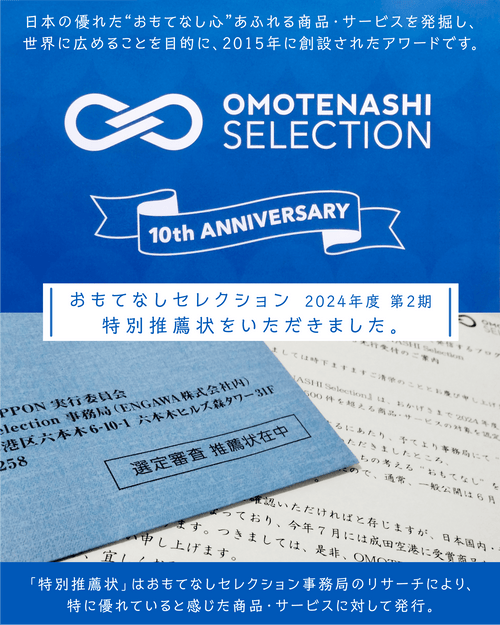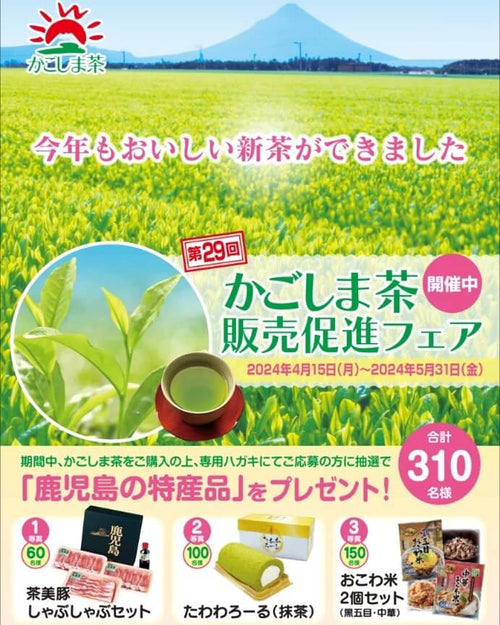関連記事
-

お茶と私と、マイボトル
連載茶話18「心弾む春は、お気に入りのマイボトルを片手に」
-

スウェーデンの“フィーカ”に学ぶ、休むことの大切さ
スウェーデンで日常的に使われるフィーカ(FIKA)とは?
-
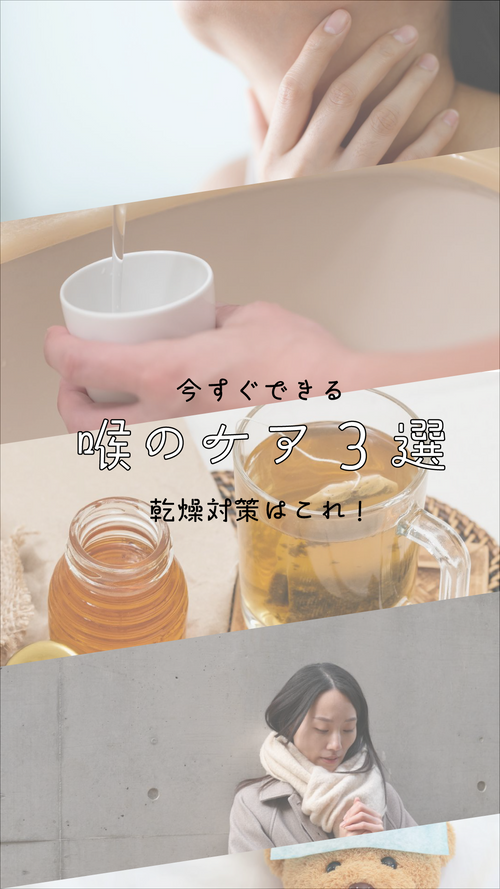
今すぐできる『喉のケア』3選 冬の乾燥対策はこれ!
冬の乾燥は、体調不良や肌荒れといった不調を招く要因となります。
-

疲れた体に休息を!休息に最適な食材10選
現代社会でストレスを抱える方におすすめの食材10選
-

一杯の知覧茶が、日常の中に小さな“間”をつくる。
休憩は、ただ止まる時間ではありません。
次の動きを軽くするための準備時間です。 -

帰省手土産に、“ひと息”を贈る| 夏のお茶ギフトのすすめ
帰省手土産は、「静かなごほうび」を贈るという選択
-

冷たくて、やさしい。夏のお茶じかん
ふとした瞬間に、「あ、ちょっとしんどいな」と感じること、ありませんか?
-
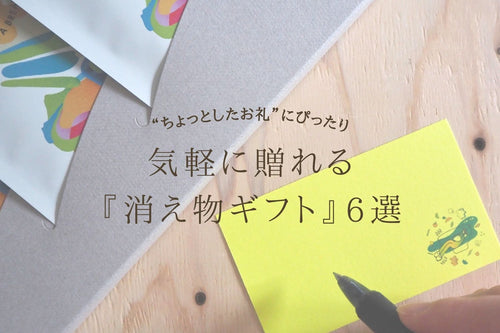
“ちょっとしたお礼”にぴったり 気軽に贈れる『消え物ギフト』6選
そっと気持ちを届ける、日常をさりげなく豊かにする消え物ギフトのすすめ。
-

贈り物にお茶を。選ぶときのポイントとは。
お茶は性別や年齢を問わず、さまざまなシーンで楽しめるのも大きな魅力。
-

新茶の魅力とは?香り・旬・栄養から紐解く、春だけの特別なお茶
春の訪れを告げる「新茶」は、香り・味・栄養、どれをとっても特別。
なぜ“新茶はいい”と言われるのか?その理由も丁寧に紐解きます。 -

目から鱗の『カテキンパワー』を知る
カテキンは「辻村みちよ」という日本人女性によって発見されました
-

秋の味覚を楽しむ!おすすめのお茶5選
少しずつ変わる季節。秋にぴったりのお茶のご紹介。
-

海外から見た日本茶の魅力: 煎茶、抹茶、ほうじ茶の世界を探求する
海外の人々が日本茶に魅了される理由、そしてその魅力を探求します。
-

おすすめの飲み方「茶葉をミルする」
お湯でもなく水出しでもなくミルして飲むお茶
-

おすすめの飲み方「水出し緑茶」
これからの季節に!水を入れるだけで美味しいお茶
-

さらに美味しくなるティーバッグの淹れ方
ちょっとしたポイントで美味しくなる淹れ方
-

お茶の効能をもう1度見直してみませんか?
「ストレスの緩和」「アンチエイジング効果」「食生活を整える」の3つをご紹介
-

知覧茶について|産地・品種・特徴
なんと市町村別の生産量では全国1位です
-

リーフ(茶葉)とティーバッグの違い
お茶初心者のためのリーフとティーバッグのメリット・デメリット
-
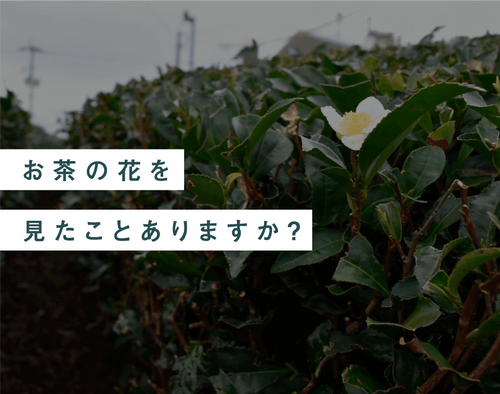
お茶の花を見たことありますか?
茶畑は花畑にならない?!
-
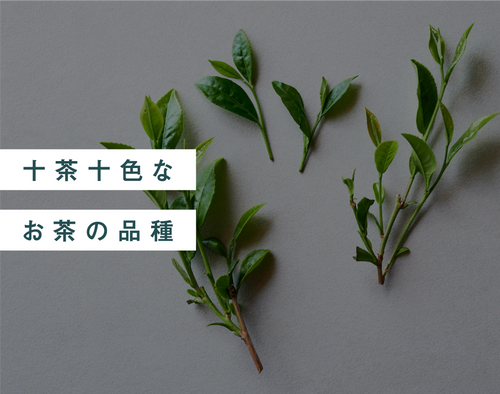
十茶十色なお茶の品種
品種で選ぶのも面白いですよ
-
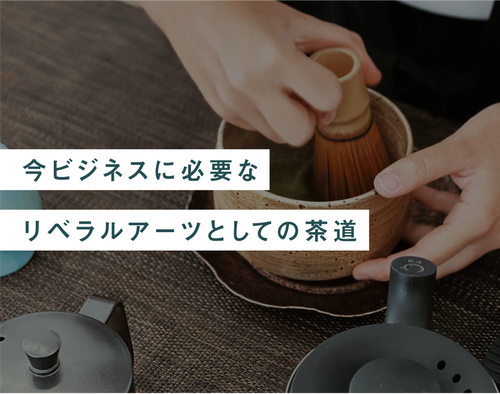
ビジネスに必要な茶道
ビジネスパーソンのための茶道
-

秋にお茶のひとときを
秋の魅力をお茶とともに
-
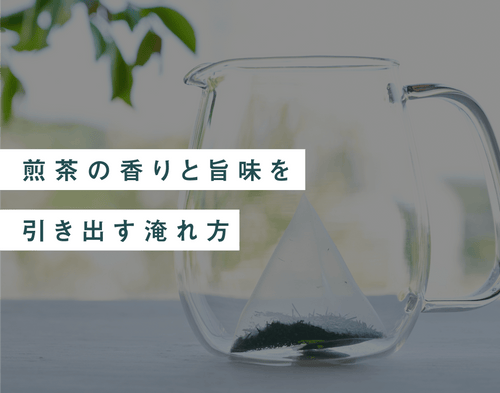
煎茶の香りと旨味を引き出す淹れ方
煎茶の風味や香りを最大限に楽しむポイント
-
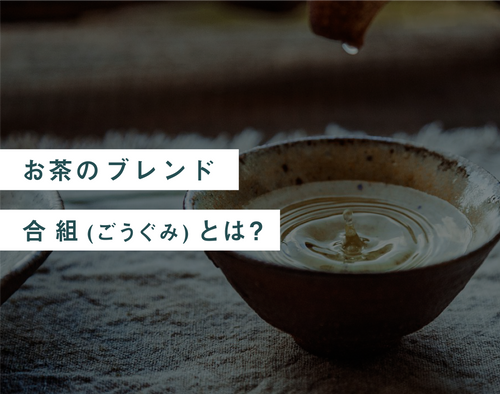
お茶のブレンド 合組とは?
目、鼻、舌、手触り。感覚を研ぎ澄ます。
-

【中止になりました】イベントのお知らせ〜玄米茶と和紅茶〜
11/26(水)10:00〜11:30(華と薫り アトリエ)ご予約優先、先着5名。
-

法人様・大口注文窓口のご案内
委託販売・卸売販売・業務用・ノベルティなどをご検討の方へ。
-
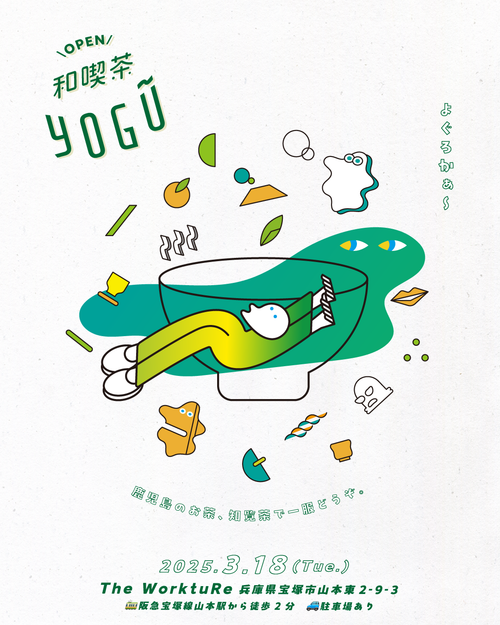
【出店】初\OPEN/ 和喫茶YOGŪ|兵庫県宝塚市
3月18日 宝塚市の素敵カフェThe WorktuReさんで、YOGŪ初のワークショップを開催します。
-

価格改定のお知らせ
2025年3月1日受注分より一部商品の新価格を適用いたします
-

「かごしま標章茶規格基準」審査に合格しました。
「外観」「水色」「香気」「滋味」を審査
-
![委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]](//yogu.jp/cdn/shop/articles/logo-wide2.jpg?v=1724813348&width=500)
委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]
最高のプレゼントに出会える場所
-

鹿児島県|KOFF COFFEE様 取扱開始
鹿児島抹茶「挽」と知覧ほうじ茶「焙」を使ったドリンクの提供開始
-
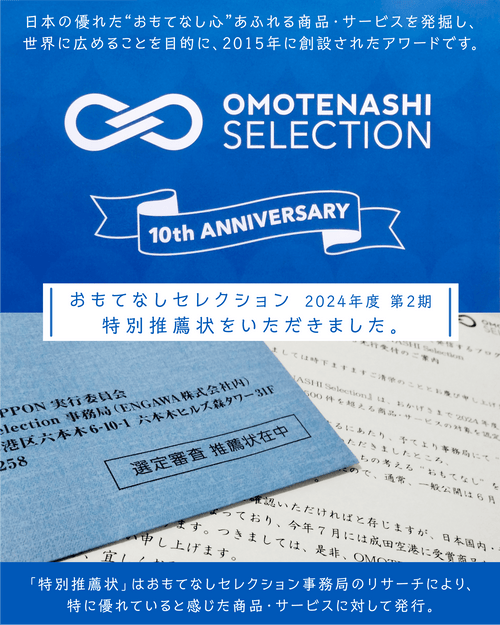
おもてなしセレクション様から特別推薦状をいただきました
「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」
-
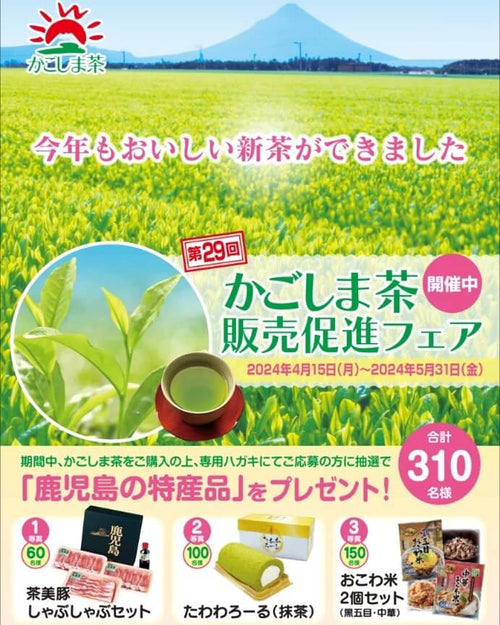
第29回かごしま茶販売促進フェア(春期)
抽選で310名の方に鹿児島の特産品をプレゼント
おすすめ商品
-
YOGŪのお茶おためし便|トライアルセット|送料185円商品
販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,300通常価格単価 / あたり -
【ギフト】YOGŪ 知覧茶 50g(リーフ)|お茶用ドリップバッグ(空袋)10枚入
販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,500通常価格単価 / あたり -
【ギフト】YOGŪ 知覧茶 一煎(リーフ)|小みかん(ティーバッグ)|ゆず(ティーバッグ)
販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,100通常価格単価 / あたり -
【ギフト】YOGŪ 知覧茶 一煎(リーフ)×2|ドリップバッグ×2
販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥900通常価格単価 / あたり -
 売り切れ
売り切れYOGŪ 知覧茶|一煎 (リーフ)
販売元:知覧茶専門店 YOGŪ5.0 / 5.0
(11) 11 レビュー数の合計
通常価格 ¥280通常価格単価 / あたり






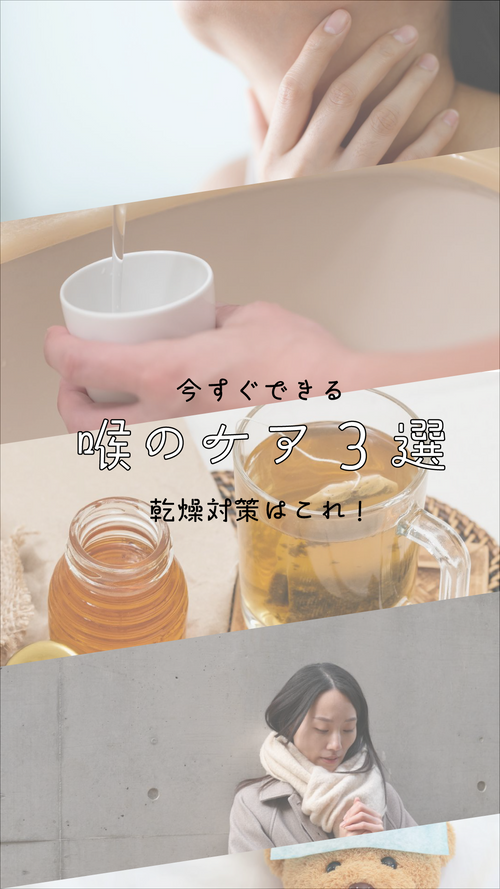




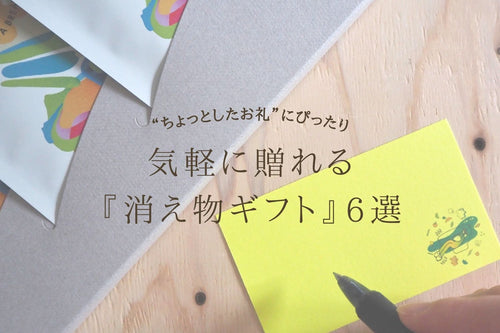











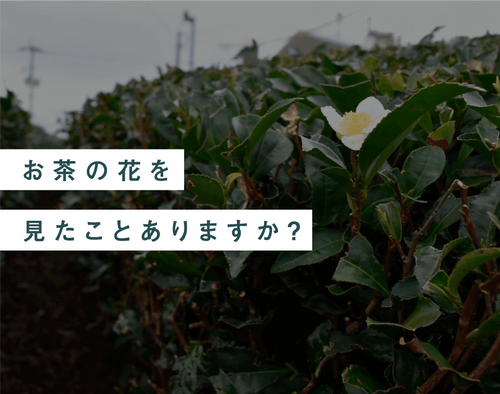
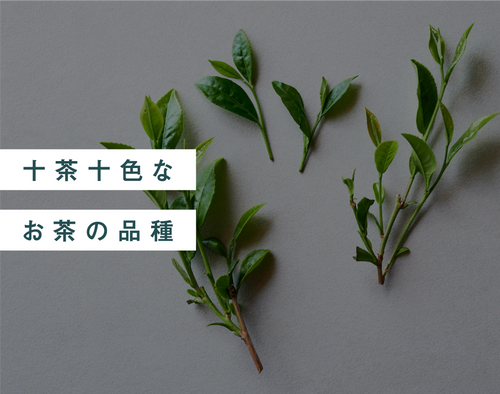
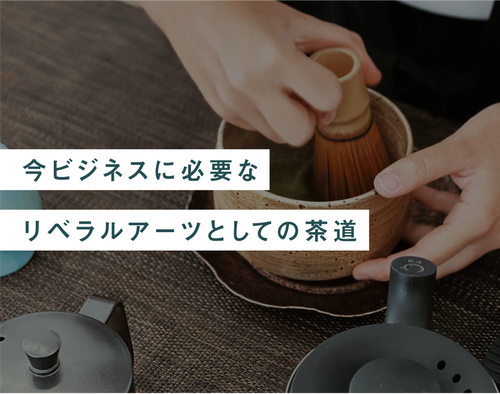

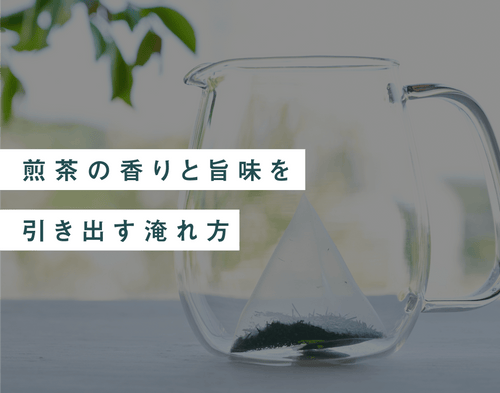
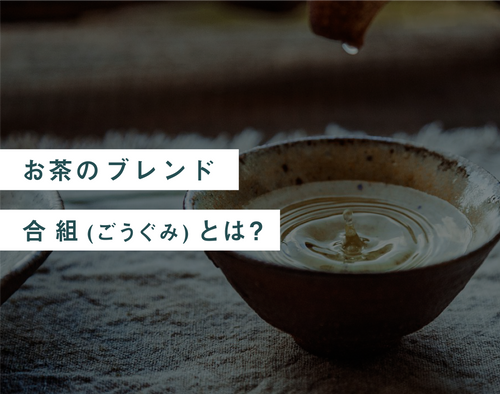


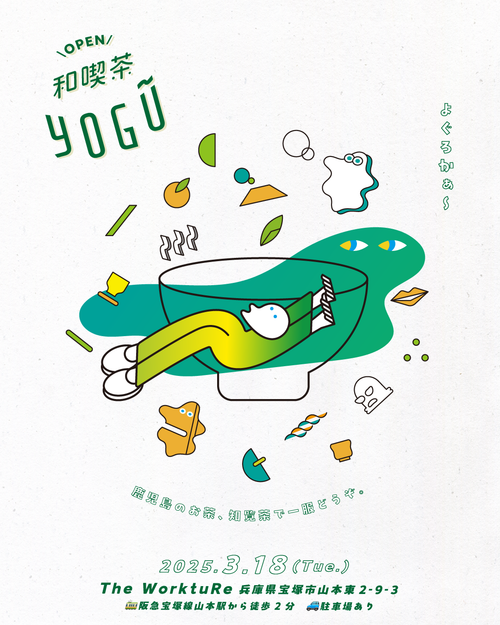


![委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]](http://yogu.jp/cdn/shop/articles/logo-wide2.jpg?v=1724813348&width=500)